愛されたい、愛したい──その想いが人を強くする
2025/01/28
愛されたい、愛したい──その想いが人を強くする。そんな考えを土台に、少しお話をさせてください。私の仕事は、身体と心が繋がっていることを大切にしています。そのため、広い視野を持つために心理学を学び続けています。最近、「子ども基本法と再養育」をテーマにした講義を受け、自分の知識や経験の浅さを痛感する瞬間もありました。「何もできていない」と思うこともありますが、それすらも学びの一部だと感じています。
ただ、私は誰かの“救い主”になりたいわけではありません。この世の中では「答えを見つけること」が重要視されがちですが、私は「答えがなくてもいい」と考えるようになりました。人生には簡単には解決できない問題が少なくありません。そんなとき、肩の力を抜いて、深呼吸をする。頭ではポリヴェーガル理論でいう腹側迷走神経系(安全・社会性)が働きだす。それが身体をリラックスさせて心の安心感を取り戻させる。まずは「呼吸を意識して使いこなせるように」とお伝えしたいです。
2023年4月に施行された「子ども基本法」は、すべての子どもが大切にされ、基本的人権が守られる社会を目指しています。この法律により、親も支援を求めやすくなり、子育てが少しでも楽になることが期待されています。親が安心して子育てできる環境は、子どもたちの未来だけでなく、良い大人が増える期待が高まってくるでしょう。
ここで、記憶の不思議さについて少し触れたいと思います。記憶とは、「真実」をそのまま留めるものではなく、「どのように思い出されるか」が重要だと言われています。匂いや感覚などが再構成される記憶は、過去の出来事そのものに囚われる必要はなく、そこから何を感じ取るかが大切だと教えてくれます。
人は、優しさや思いやりを通じて強くなることができます。他者を受け入れ、距離を縮めることができますが、自分を見失わないための「匙加減」も必要です。だからこそ、無理に答えを出そうとせず、「ぼんやりとした姿勢」も選択肢の一つとして受け入れてほしいと思います。自分を追い込みすぎず、余白を持つことが大切です。これにも呼吸が活用できますね。
辛い経験をしたとき、その解決は決して簡単ではありません。まずは「自分に原因があるわけではない」と認めることから始めてみましょう。そして、自分が持っているものに目を向け、そこにどんな意味があるのかを考えることが大切です。言葉でかくと簡単にかけてしまうのですが、こちらは我慢強くあきらめずに取り組むことになります。できれば、信頼できるカウンセラーと一緒に行うことが良いですが、自分で対処できない場合は専門家へ協力を求めることを頭の片隅に置いておきたいところではあります。
もし自分で救いがあるとするなら、それは「自分自身を認める」ことから始まります。たとえば、「泣いてもいい」と自分に許可を出すこと。それが、少しずつ前に進むための第一歩になるのではないでしょうか。たとえば、音楽を伴走すると効果があるようです。
最近、「それはあなたの感想ですよね」という言葉が子どもたちの間で流行していると耳にしました。この言葉には、トラウマを抱える人が「感情を自分のものとして受け入れる」大切さが隠されているように感じます。特に50代の女性が自分の心と向き合い、優しく癒していくためのヒントになるかもしれません。
最後に、人間関係がこじれてしまったとき、自分がその相手に対して負の感情を抱くこともあります。そんな相手に直接会うことはないかもしれませんが、「ありがとう」という感謝の気持ちを持てるようになることが、自分を受け入れる第一歩なのかもしれません。頭でわかっていてもそうならないのも人。だから私は定期的学びを繰り返すのかもしれません。
-
 夜のケアが決め手!50代からの睡眠で変わる見た目年齢
🌙良質な睡眠が「見た目年齢」を変える50代からの美しさは、夜つくられる ——「最近、眠りが浅い気がす
夜のケアが決め手!50代からの睡眠で変わる見た目年齢
🌙良質な睡眠が「見た目年齢」を変える50代からの美しさは、夜つくられる ——「最近、眠りが浅い気がす
-
 見えていなかった不調に、やさしく光が当たる瞬間
人に触れてもらうと、自分では気づけなかったことに気づく。もちろん、誰でもいいわけじゃなくて、信頼して
見えていなかった不調に、やさしく光が当たる瞬間
人に触れてもらうと、自分では気づけなかったことに気づく。もちろん、誰でもいいわけじゃなくて、信頼して
-
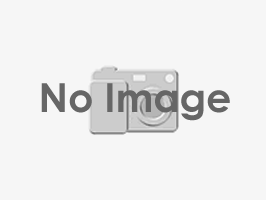 「忙しい50代キャリア女子へ。
“全身伸び”で疲れをひと呼吸リセット」
「忙しい50代キャリア女子へ。“全身伸び”で疲れをひと呼吸リセット」毎日、仕事に家事にスケジュールぎ
「忙しい50代キャリア女子へ。
“全身伸び”で疲れをひと呼吸リセット」
「忙しい50代キャリア女子へ。“全身伸び”で疲れをひと呼吸リセット」毎日、仕事に家事にスケジュールぎ
-
 50代の肌に届く“小さな応援メッセージ”
──エクソソームが教えてくれる再生のしくみ──
50代の肌に届く“小さな応援メッセージ”──エクソソームが教えてくれる再生のしくみ──**■こんな変
50代の肌に届く“小さな応援メッセージ”
──エクソソームが教えてくれる再生のしくみ──
50代の肌に届く“小さな応援メッセージ”──エクソソームが教えてくれる再生のしくみ──**■こんな変
-
 忙しい50代のあなたへ。実は一番“放っておけない場所”の話
[#機能置換タグ_TOC:目次#]50代からの身体を守るために──“フェムゾーン”という新しい考え方
忙しい50代のあなたへ。実は一番“放っておけない場所”の話
[#機能置換タグ_TOC:目次#]50代からの身体を守るために──“フェムゾーン”という新しい考え方
-
 追い込まない。50代の体が応えてくれた、腸と呼吸の整え方
[#機能置換タグ_TOC:目次#]50代からの「なんとなく不調」に、呼吸という選択を最近、「どこが悪
追い込まない。50代の体が応えてくれた、腸と呼吸の整え方
[#機能置換タグ_TOC:目次#]50代からの「なんとなく不調」に、呼吸という選択を最近、「どこが悪




